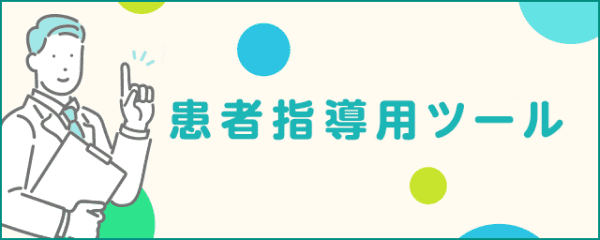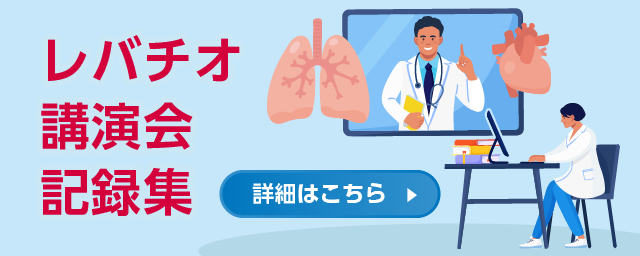Viatris e Channelは、医療従事者向けの総合情報サイトです。
ご利用にあたっては以下の利用条件をご覧ください。
- ■ご登録は医療機関にお勤めの医療系国家資格保有医療従事者に限らせていただきます。
- ■原則、会員登録はお一人様につき、1アカウント(ID)のみとさせていただいております。
- ■以下の場合、通知をすることなく会員の資格の取り消しを行うことがございますのでご了承ください。
- ・登録内容の変更において、医療機関にお勤めではなくなられた場合
- ・登録内容に虚偽が判明した場合
- ・会員の死亡、転出先不明等により、弊社が合理的な通信手段を用いても会員ご本人と連絡がとれなくなった場合
- ■その他、ご利用にあたっては利用規約とプライバシーポリシーが適用されるものとします。
弊社は、厚生労働省「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン」に則り、提供相手方のお名前・ご施設名を記録させていただいております。閲覧をご希望される際には、お名前・ご施設名を入力いただきますのでご了承ください。なお、入力いただいた情報、および閲覧された資料は、以下の利用目的の範囲で利用記録として収集、記録、保存させていただきます。収集した個人情報は以下の目的のみに利用いたします。
利用目的:情報の提供先の把握、記録、保存。
取得した個人情報の取り扱いに関しては、弊社のプライバシーポリシーをご参照ください。
一部製品において、ご提供いただいたお名前、ご施設名をヴィアトリスグループ会社間に共有させて頂くことがあります。
「Q&A*」ページには以下の情報が含まれております。ご利用に際しては、ご利用者において十分ご留意ください。
- ・承認された事項(用法用量、適応、剤形など)以外の情報
- ・未承認の製品に関する情報
- ・販売を中止した製品の情報
なお掲載されている全ての情報は、無断で複製すること、第三者に頒布することを禁止いたします。
*:Q&Aの一部のコンテンツは、海外で作成した資料のため日本の文献情報等が一部含まれていない場合もございます。また、最新の情報をお届けするために、要旨、電子添文情報、免責条項以外は海外で作成した英語原文での回答とさせていただいてるコンテンツもございます。
以上の事項に同意のうえ、ページを移動しますか?